こんにちは、わかです!
前回は、東洋医学の基本である気・血・水とそれに関わる6つの不調タイプからみる体質についてお伝えしましたね。
今日は、和漢薬膳で注目すべき食材のパワーやバランスタイプについて、またどの体質タイプの人がどんな食材を取り入れると良いのかを解説したいと思います。
人間の体と同じように、食材にもそれぞれ特質があり、自分に合った食材を上手く取り入れることが大切です。しっかり学んで、日々の食事に取り入れていきましょう!
味覚の五つの基本要素、「五味調和」
いきなり聞き慣れない言葉が出てきましたが、東洋医学と食べ物の関係として基本となる考え方なので、ちょっと我慢して読んでくださいね。
東洋医学では、自然界も人間の体もあらゆるものを五つのタイプに分ける、「五行説」という考えがあります。この五つの要素がそれぞれ助け合ったり、抑制しあうことで、あらゆるバランスを保っている、というものです。
例えば、季節なら春、夏、長夏(梅雨明け後)、秋、冬。
色彩なら青、赤、黄、白、黒のように、様々な事柄の分類が決まっているんです。
味覚は、五行では以下の五つに分類され、「五味調和」と呼びます。
甘、酸、苦、辛、鹹の五つです。
それぞれの「味」には身体の機能を高めたり、逆に機能を損ねる効果となるものがあります。それぞれの特徴を理解し、自分の体質やその時の体調に合ったものを選択することで、身体のバランスを調整することができます。
以下に五つの味の良い働きと、逆に機能を損ねてしまう働き、代表的な食材を記載します。
その時々で自分の体に必要な働きや、注意が必要な機能を意識して取り入れてみてください。
- 甘味
効果:滋養強壮、緊張を緩める 悪い効果:体がだるくなる、髪が抜けやすい
代表的食材:大根、かぼちゃ、にんじん、肉類、牛乳、松の実、ごまなど - 酸味
効果:血液浄化、肝臓や目に良い 悪い効果:胃を弱める
代表的食材:梅、トマト、柑橘類、りんご、お酢など - 苦味
効果:熱を下げ、余分な水分を排出する。頭痛、めまいに良い 悪い効果:胃腸を冷やす、風邪をひきやすい
代表的食材:パセリ、ワラビ、緑茶、コーヒーなど - 辛味(からい)
効果:発汗、血行促進、身体を温める 悪い効果:肝臓を弱める、汗をかきすぎて冷える
代表的食材:パねぎ、生姜、にら、にんにく、唐辛子など - 鹹味(しおからい)
効果:粘膜を潤す 悪い効果:血圧が上がる、血液がねばる
代表的食材:昆布、塩、アサリ、しじみ、海苔、醤油、味噌など
食べ物の五行と寒熱の体質
食べ物そのものも、体を温める性質の強いものから冷やす性質の強いものまで、「熱・温・平・涼・寒」の五つのタイプに分類できます。またそれらを更に覚えやすく、以下の三つに分類することもあります。
「温熱性食品」:体を温める性質を持ち、新陳代謝を高める
「涼寒性食品」:体を冷やして熱を取り、鎮静効果や瀉性作用を持つ
「平性食品」:どちらにも偏らない。滋養強壮の作用をバランスよく持つ
前回、東洋医学の基本である気・血・水から東洋医学の体質について説明しましたが、より感覚的にわかりやすい体質判断として「寒体質」と「熱体質」があります。
寒体質の人は「温熱性食品」を取って体を温めることが体調を整えることにつながりますし、熱体質の人は「涼寒性食品」を取ることで体の余分な熱を取り、バランスの取れた「中庸」の状態にすることができるのです。
「寒体質」の人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 夏の暑さに強い
- 体格は痩せ型が多く、なで肩
- 手足が冷たく、指が細い
- 顔色は青白い
- 耳の中が乾燥している
- 舌の色が薄く、苔が白い
- 胃腸が弱く、下痢をしやすい
- 生理周期は長め
- 睡眠時間は長い傾向
「熱体質」の人の特徴としては、以下のようなものが挙げられます。
- 冬の寒さに強い
- 体格はがっしりしていて、いかり肩
- 手足は温かく、指が太い
- 耳垢は湿っている
- 舌の色が濃く、苔が茶色っぽい
- 胃腸が強い
- 便秘気味
- 生理周期は短め
- 睡眠時間は短い傾向
どうでしょうか?どちらかの要素が多く当てはまる!という場合には、ぜひその性質を弱めて、寒でも熱でもない真ん中の状態に持っていくために、以下を参考に自分の体質とは逆の特徴を持つ食べ物を意識して取るようにしてみてください。
温熱性食品(体を温める性質を持ち、新陳代謝を高める。)の例
玉ねぎ、かぼちゃ、ピーマン、小松菜、カブ
ししとう、生姜、にら、ねぎ、ニンニク、赤唐辛子
サワラ、鮎、アジ、イワシ、エビ、鯛、ブリ
桃、さくらんぼ、みかん、柚子
牛肉、鶏肉、羊肉
酒、味噌、酢、わさび、ごま油、黒砂糖、胡椒
クルミ、チーズ、紅茶
涼寒性食品(体を冷やして熱を取る。鎮静効果や瀉性作用を持つ。)の例
たけのこ、セロリ、トマト、蓮根、大根、レタス、ごぼう、なす
きゅうり、ほうれん草、もやし、白菜
アサリ、しじみ、カニ、わかめ、昆布、ハモ
バナナ、いちご、メロン、スイカ、柿、梨、オレンジ
ベーコン、豆腐
塩、白砂糖、醤油
小麦、そば、海苔
平性食品(どちらにも偏らない。滋養強壮の作用をバランスよく持つ。)の例
キャベツ、アスパラガス、じゃがいも、とうもろこし、インゲン
にんじん、さつまいも、ブロッコリー、水菜、チンゲン菜、椎茸
ハマグリ、牡蠣、秋刀魚、サバ、スズキ、カレイ、ヒラメ、タコ、ホタテ、イカ
いちじく、梅、レモン
豚肉、鴨肉、卵、牛乳
ごま、きな粉、はちみつ、ヨーグルト
米、うどん、納豆、パン
まとめです。
・味覚の五行である五味調和の酸、苦、甘、辛、鹹(塩味)にはそれぞれ体に与える良い働きと、逆に機能を損ねる働きがある。
・寒体質の人は体を温める温熱性食品をとり、熱体質の人は体を冷ます涼寒性食品を意識して取ることで、どちらでもない真ん中の状態に持っていくことができる。
以上。今回は、東洋医学の五行の考え方をもとに、味と食材の性質と効用、またそれぞれどのようなタイプの人が食べると効果的かをご紹介しました。
自分の体質に合わせて、上手に食材の持つ力を取り入れてみてくださいね!

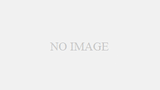
コメント